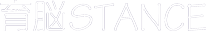いつから勉強が嫌いになる?
最近、様々な場所で子ども達の勉強の話がよく題材として上がるようになってきたように思います。
それも小学生の段階での保護者さんから続々と・・・
これはプログラミング的思考だとか、新しい学習要領のことが、訳がわからないからこういう状況を生み出しているのか?
それとも子どもの数は減っているのに対し学校の数が多すぎることへの懸念からなのか?は、わかりません(後者であってほしいとは思いますが・・・)が親が子どもの学力について、幼少の頃から気にすることは子ども達にとってもすごくいい現象だと喜んでおります。
このような機会が増えた中で育脳スタンスが「学び方を教える塾」だということもあるのかもしれませんが「子どもはいつから勉強が嫌いになりますか?」とか「どうすれば、勉強が嫌いにならない様になりますか?」などの質問をいただくことがよくあります。
ですので、少し私共の見解を記しますので、ご参考程度にお読みいただければ幸いです。
「子どもはいつから勉強が嫌いになるのか?」という質問から・・・
「いついつから勉強を嫌いになります!」などという宣言が行われる訳ではないので、一概にいつ頃からと断言することはできないでしょう。
ただ、学年にもよるところがあるのですが、小学1年生ぐらいまでの児童であれば、そのひとつの要因として考えられているのが「気持ちの切り替え」ができるか?どうか?でしょうか・・・
まずは小学校が始まることで、子ども達を取り巻く環境は大きく変わります。
これまではある程度の制限はあるものの、やりたいことが優先される園生活を送ってきましたが、急に学校という別のルールに従わなくてはならない状況に一変します。
この時の「気持ちの切り替え」ができる子どもは何も思わず、もしくは園生活に飽きていた子なら尚更学校生活が楽しくなるかも知れません!しかし、園生活から切り替えができなかった場合は、どうなると思われますでしょうか?
学校に行く様になってから、嫌なことが増えた様な気になっても、おかしくないのではないでしょうか?
人間の脳は3秒間以内に「好き」「嫌い」を判断すると言われています。
いわば、無意識レベルで自分の好きや嫌いにあたる気持ちが既に決まっているということになります。
であるならば、どの様な理由や状況にしろ「やらない、やりたくない」というマイナスな感情を生みやすい生活を続けるよりは、「やりたい、やってみたい」とプラスの感情を生み、好奇心として自分の気持ちをコントロールできることが大切だと考えています。
子ども達が大きくなるに連れ、様々な理由で矛盾や理解のできないことが増えます。
この様なことは皆さんも多く経験されて来たことだと思います。
なので、当たり前のことだと思われるかもしれませんが、そうでしょうか?
子どもが子どもなりの世界観で感じたままに受け取らせてしまうのと、子どもが前向きに理解できる様に大人が解釈してから受け取らせるのとでは、同じ経験であったとしても子どもの心に残る経験値としては全く別物になるのではないでしょうか?
なぜなら、子どもは大人の様に「メリットか?デメリットか?」ではなく、自分にとってどうであるか?は人生経験が少ない子ども達にとってはよくわからないことなので「好きか?嫌いか?」だけで判断するしかなくなります。
ましてや、自分の気持ちで決めたのではなく、親が勧めることで決まったことや訳のわからないうちに決まったことであれば、尚更「よし!」となるはずがありません。
理解できないことや矛盾が多くなると「よくわからない」ので「面白くない」と思ってしまうことが増えてしまいます。
だから、良い方向に気持ちが向くことがなくなるので、瞬間的に好んで選ぶことは内向きな考え方ばかりになってしまいかねません。
この経験の対象と同じ現象が、勉強をしている時にも起こっていたらどうでしょうか?
それでも勉強を好きなままで、過ごすことができると思いますでしょうか?
結果は、一目瞭然です。
だから結論から申しますと「子どもはいつから勉強が嫌いになりますか?」も同様。
理解できてないことやわからないことを、そのまま何となく過ごし始めた時点で勉強が嫌いになるアルゴリズは動き始めているかもしれません。
是非とも、そうならない様に可能な限りわからないことをそのままにしない様にしてあげてください。